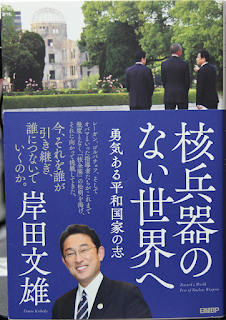第25回 してはならぬ二十箇条

またまた二つの雑誌を並べてみた。ほんとうは貴重な史料なのでこんなふうに開いて痛めるリスクを与えたくはないのだが、現物を見てもらうには、ま、致し方ないというところかな。ということで、本題に入ります。 これは前回紹介した両誌の明治41年7月に発行した号のそれぞれのとある頁である。『家庭之友』には「母親のしてはならぬ事(二十四ヶ条)」、そして『婦人之友』には「主人のしてはならぬ事(二十箇条)」というよく似た記事が載っているのだ。二誌を並行して編輯・発行していた羽仁もと子ならではのお遊びとも思えるので、こちらも遊んでみたい。 まずは左側の『家庭之友』の「母親のしてはならぬ事(二十四ヶ条)」という記事である。写真では見にくいだろうから、以下に記事を転載する。仮名遣いなどは最小限ではあるが、現代風に改めておいた。 ************************************** 母親のしてはならぬ事(二十ヶ条) 一、子供の中のある一人を偏り愛してはならぬ事。 二、少しぐらい言うことを聴かぬとて、いちいち子供を責めたててはならぬ事。 三、愛を含んで厳格にするのはよいけれど、ガミガミと小言をいってはならぬ事。 四、何故にその事の悪いかを教えずに、一方的に子供をおどしつけてはならぬ事。 五、早速に実行の出来ないことを子供に約束してはならぬ事。 六、子供を召使のみ任せて置いてはならぬ事。 七、子供を驚かすようなことをしてはならぬ事。 八、子供を叱り、または懲らしめる場合に、怒りを以てしてはならぬ事。 九、同じく子供を叱り、または懲らしめる場合に子供を辱(はずかし)めてはならぬ事。 十、喰い過ぎをさせてはならぬ事。 十一、子供のいろいろな質問に対して、飽きたり五月蠅(うるさ)がったりしてはならぬ事。 十二、子供の自信を傷つけるようなことをしてはならぬ事。出来るだけ自信を養わせるように勇気づけてやらねばならぬ事。 十三、子供がなにかしようとする時に、それを貶(けな)したり妨げたりしてはならぬ事。むしろどうしたらそれを能くすることが出来るかについて教え導いてやらねばならぬ事。 十四、子供の教育に関して、みだりに父親の意見にさからってはならぬ事。 十五、太陽の光、新鮮なる空気の中に、子供を出すことを忘れてはならぬ事。 十...